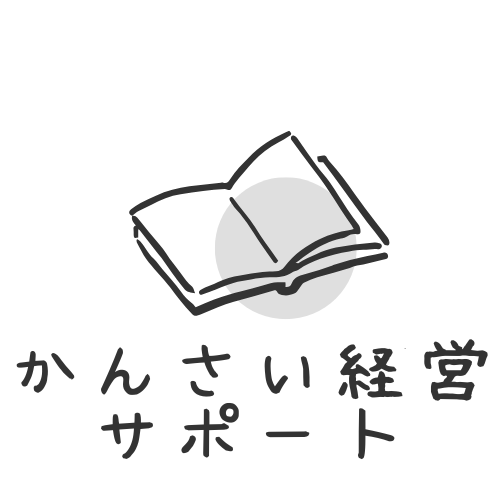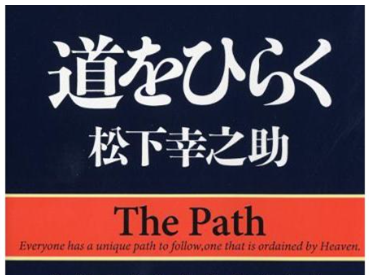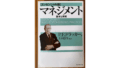日々意思決定に追われる経営者にとって、松下幸之助の『道をひらく』は、時代を超えて心に響く一冊です。
1968年の出版から半世紀以上を経てもなお、多くの経営者が座右の書として挙げる理由は、この本が「人間の本質」を見つめ続けているからに他なりません。
1.「断を下す」――迷うより、まず決める勇気を持つ
松下幸之助はこう語ります。
「要はまず断を下すことである。みずから断を下すことである」
経営の現場では、正解が見えない中で決断を迫られる瞬間が多々あります。
そのとき重要なのは、「どちらが正しいか」ではなく、「自ら断を下す勇気」を持つこと。
決められないリーダーの下では、社員も動けません。
経営とは、未知を切り開く決断の連続です。
迷いを断ち、まず一歩を踏み出す――その決断力こそ、経営者の最大の責務ではないでしょうか。
2.「素直な心」――経営改善の原動力は、謙虚さにある
『道をひらく』で繰り返し登場するキーワードが、「素直な心」です。
松下氏の言う「素直さ」とは、単なる従順ではなく、私心を捨て、ありのままを受け入れる心のこと。
たとえば、
①社員の提案を否定から入っていないか
②過去の成功体験に偏ってはいないか
③「自分のやり方」に固執していないか
この“心の姿勢”を見直すことが、経営改善の第一歩です。
中小企業ではトップの考え方が組織文化をつくります。
社長が素直であれば、組織全体も素直になります。
素直な会社には、学びと変化の兆しが自然と現れます。
3.「熱意」――才能よりも、燃える心が経営を動かす
松下氏は言います。
「才能がハシゴをつくるのではない。やはり熱意である。」
事業は不思議なもので、いくら経験を積んでも「これで完成」という境地はありません。
むしろ、経営とは底なしに深く、限りなく広い世界です。
だからこそ、必要なのは知識よりも「熱意」。
“どうしても二階に上がりたい”という熱い気持ちが、ハシゴを発想させ、階段を生み出すのです。
今、業績が厳しいと感じるときこそ、問いかけましょう。
「私は本当に、この事業に熱意を持っているだろうか?」
熱意を取り戻すこと。それがすなわち、会社の未来をひらくことにつながります。
4.『道をひらく』が今の時代に必要な理由
この本が書かれたのは、高度経済成長のまっただ中。
日本が豊かになる一方で、心の貧しさが問題視され始めた時代でした。
そして現代。AI、デジタル、人口減少と、私たちは再び「正解のない時代」を生きています。
だからこそ、松下氏の言葉が改めて価値を持つのです。
彼の哲学は、単なる経営論ではなく、「人間としてどう生きるか」という根本に立ち返らせてくれます。
5.中小企業の経営に活かす3つの実践ポイント
①即断・即行
完璧な情報を待つより、小さく決めて動く。現場で修正する。
②素直に学ぶ
社員、顧客、取引先、すべてが“師”。現場の声に耳を傾ける。
③熱意を伝える
社長の情熱は伝染する。理念・ビジョンを繰り返し語り続ける。
終わりに
『道をひらく』とは、単に人生訓の本ではありません。
それは「経営者としての心の整え方」を教えてくれる指南書です。
道は外にあるのではなく、心の中にあります。
経営の悩みや不安を抱えるときこそ、ぜひページをめくってみてください。
そこには、“経営の原点”が書かれています。