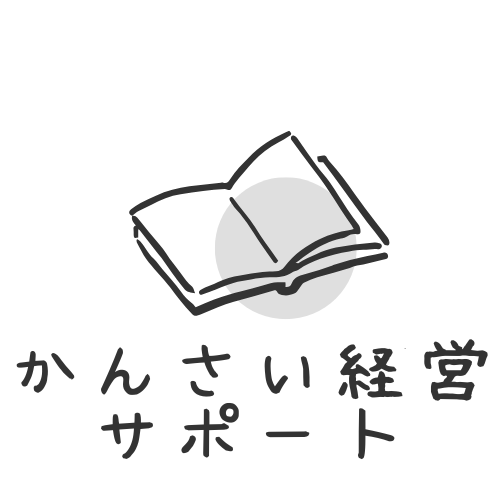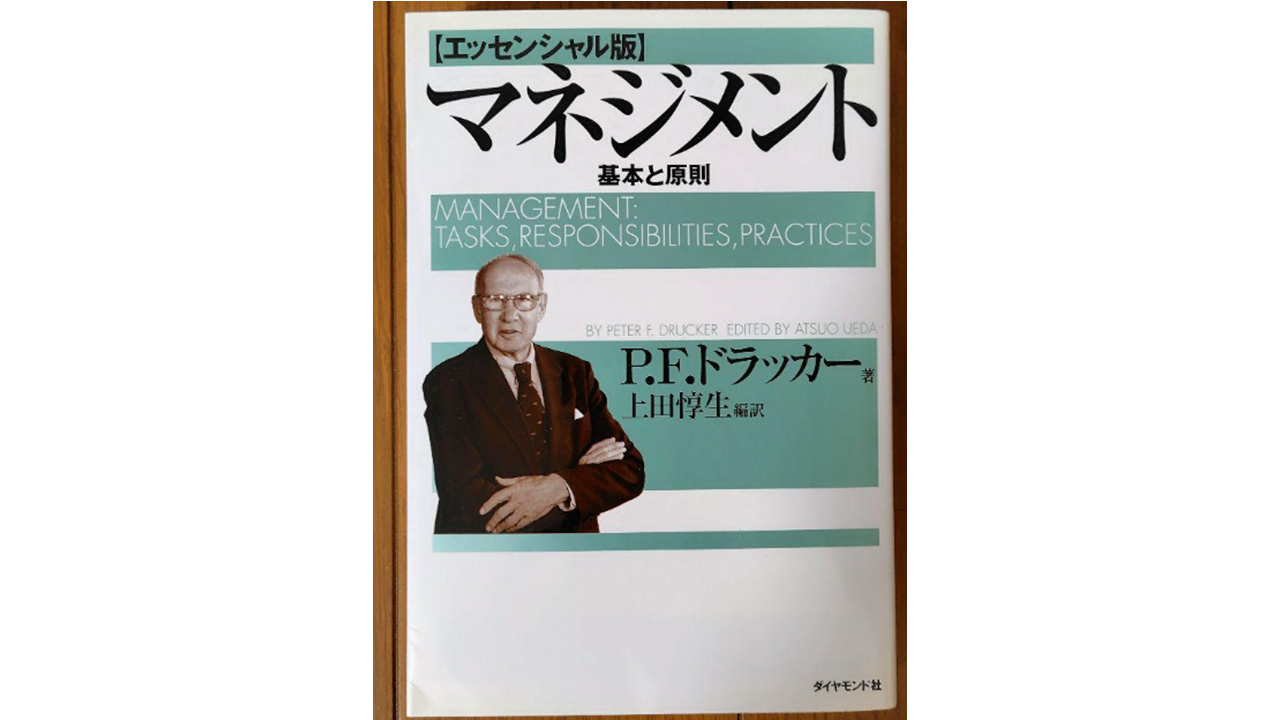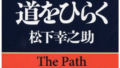はじめまして。中小企業診断士の西田雄一郎です。
私が読んだ本の気づきなどを皆さんと共有できればと思い、ブログを作成します。
これが第1回目となります。引き続き宜しくお願い致します。
中小企業こそドラッカーのマネジメントを活かせる理由
―利益よりも「目的」から始める経営へ―
「うちの会社は小さいから、ドラッカーなんて関係ない」
そうおっしゃる社長に、私はよく出会います。
しかし実は、ドラッカーの言う“マネジメント”は、大企業よりも中小企業にこそフィットする考え方です。
1.ドラッカーが教える「マネジメント」の本質
ドラッカーは「マネジメントとは、組織が成果を上げるためのしくみである」と定義しました。
つまり、“管理”ではなく、“成果を上げるための活動”そのもの。
マネジメントの3つの役割は次の通りです。
1️⃣ 事業のマネジメント(顧客を創造する)
2️⃣ 人と仕事のマネジメント(人を生かす)
3️⃣ 社会的責任のマネジメント(社会に貢献する)
この3つがバランスして初めて「経営」が成り立ちます。
2.利益は目的ではなく「条件」
ドラッカーは明確に述べています。
「利益は、企業の目的ではなく、企業が存続するための条件である」
利益を出すことは当然重要です。しかし、それは「目的」ではなく「結果」。
「誰のどんな課題を解決するための事業なのか」を明確にした企業が、結果として利益を生むのです。
たとえば、ある製造業の社長が「我々の事業は何か?」と問い直したとき、
「部品を作る会社」から「顧客の品質課題を解決する会社」へと定義を変えました。
その瞬間、営業方針も社員教育も一変し、結果として利益率も向上しました。
3.人こそ最大の資産
ドラッカーは「人こそ最大の資産である」と言い切っています。
経営資源の中で、人だけが自ら学び、成長し、価値を生み出す存在です。
しかし多くの中小企業では、「人材=コスト」と見られがち。
これは大きな誤解です。
社員を「育てるコスト」ではなく、「成果を生み出す投資」として捉えると、
会社の文化と収益構造が変わり始めます。
4.マネジメントの出発点は「顧客」
ドラッカーは、「企業の目的は顧客の創造である」と定義しています。
自社を定義する出発点は社名や業種ではなく、“顧客の満足”です。
「われわれの事業は何か」
「顧客は誰か」
「顧客はどこにいて、何を買うのか」
この3つの問いを持ち続けることが、中小企業の成長戦略の第一歩です。
5.真摯さこそ経営者の最大の資質
ドラッカーは「真摯さなくして組織なし」と言いました。
経営者が誠実であるかどうかは、社員は分かっています。
中小企業では、社長の言動がそのまま会社の文化になります。
どんなに優れた戦略を立てても、社長自身が「真摯」でなければ、社員はついてきません。
逆に、誠実に社員や顧客に向き合う社長の姿勢が、最大のマネジメントです。
6.まとめ ― 3つの問い
1️⃣ われわれの事業は何か。
2️⃣ われわれの強みは何か。
3️⃣ われわれの価値は、誰にどのように届いているか。
この3つの問いを日々繰り返すことが、ドラッカー流マネジメントの第一歩です。
中小企業こそ、社長の想いがそのまま経営に反映される組織。
だからこそ、ドラッカーの「マネジメント」は、あなたの会社に最も活かせる理論なのです。