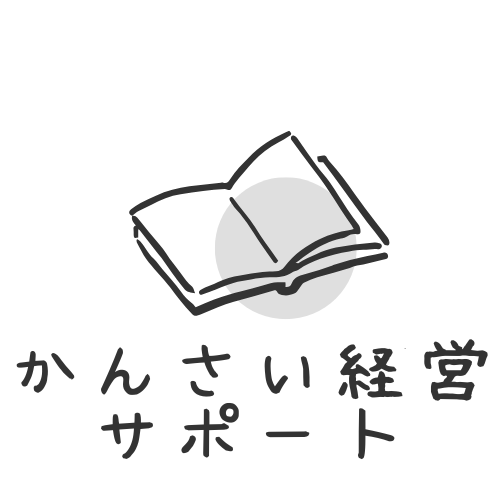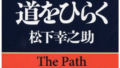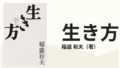昨日、大阪府中小企業診断士協会で「地域で楽しむ診断士になろう! ~仲間と見つける私らしい地域支援~」というスキルアップ研修に参加しました。
本記事では、講演内容そのものではなく、
私自身が実務にどう活かせると感じた点を中心にまとめます。
はじめに
中小企業の社長とお話ししていると、よくこんな言葉を耳にします。
「診断士さんに相談したいけど、正直、何を頼めばいいのか分からないんです。」
これは、とても正直で本質的な声です。
私たち診断士の側も、つい「支援します」「アドバイスします」と言いがちですが、実はその言葉が壁を作ってしまうことがあります。
「支援」ではなく「共創」へ
支援”という言葉の裏には、「助ける側」と「助けられる側」という構図が見え隠れします。
けれど地域で活動していると、実際はそう単純ではありません。
例えば、地元農家と一緒に行った「里山再生×クラフトビール」プロジェクトでは、
診断士も現場で汗をかき、雑草を抜き、子どもたちと笑いながら「地域の素晴らしさ」を体験しました。
その中で気づいたのは、“社長も診断士も、同じ地域の一員”だということ。
だからこそ、“共に考え、共に創る=共創”というスタンスが必要なのです。
社長の「もやもや」は、実は宝の山
「次の一歩が見えない」「整理できていない」――
そんな状態のとき、社長の頭の中には、実は“原石のようなアイデア”が眠っています。
診断士の仕事は、それを掘り起こし、カタチにすること。
完璧な計画を作ることより、まず一歩目を一緒に踏み出すことが大切です。
小さな行動が地域を変える
最初の一歩は、小さなもので構いません。
たとえば「地元の学生を巻き込む」「お客さんと一緒に企画を考える」。
そうした動きが重なれば、地域の中に自然と“エコシステム”が生まれます。
取引ではなく、共感と信頼でつながる経済圏。
これこそ、これからの地域経営の強みになるのではないでしょうか。
まとめ
地域で活動していると、診断士としてだけでなく、一人の住民、一人の親、一人の仲間としての自分に出会います。
「支援者」から「共創者」へ。
そんな関わり方が、社長にも、地域にも、そして自分自身にも新しい可能性をもたらしてくれると思います。
なお、本記事は筆者個人の理解・所感によるものであり、
講演者の公式な見解や所属団体の立場を示すものではありません。