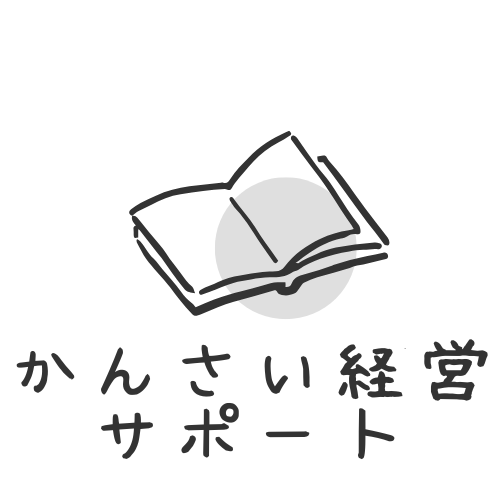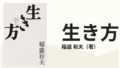昨日、プラス株式会社の淺野喜美雄副社長の講演を拝聴しました。
アスクル創業時の経験を交えながら、今の時代にこそ中小企業経営者が学ぶべき示唆に満ちたお話でした。
本記事では、講演内容そのものではなく、
私自身が実務にどう活かせると感じた点を中心にまとめます。
「発明は必要の母」——ニーズを“生む”経営へ
「必要は発明の母」とはよく言われますが、淺野氏は逆を説きました。
「発明は必要の母」——発明(新しい価値)が、必要(市場の欲求)を生む。
アスクルは、“翌日配送の文具通販”という、当時誰も必要としていなかった仕組みから始まりました。
顧客の声に応えるのではなく、「未来の声を創造する」こと。
そこにこそ市場創造の原点があるというお話に、多くの経営者がうなずいていました。
■「業態化」へのすすめ——強みを仕組みに変える
アスクルの成功は、単なる販売モデルではなく、「業態」を生み出したことにあります。
卸と小売の中間に新たな流通構造をつくり、重複コストをなくし、関係者全員が利益を得られる仕組みへ。
これは、強みや工夫を「仕組み化=業態化」することで再現性を生むという、中小企業にも通じる考え方です。
目先の改善より、「構造を変える」発想が未来を切り開く。
業態化とはまさに“0→1”の挑戦です。
■「向かい風、振りむけば追い風」——逆境を力に変える視点
バブル崩壊直後の不況期に誕生したアスクル。
まさに逆風の中で生まれた事業です。
「不況期こそ、構造を変えるチャンス」
「向かい風も、視点を変えれば追い風になる」
この言葉は、厳しい経営環境にある中小企業にこそ響きます。
変化を嘆くのではなく、変化を起こす側に回る。
その姿勢が、企業の未来を決めるのだと改めて感じました。
■おわりに—“未来の声”を聴こう
今ある顧客の声は「過去の声」。
未来の声を空想し、まだ形のないニーズを育てる。
それが、中小企業にこそできる「変化を創る経営」ではないでしょうか。
向かい風を追い風に変える視点。
そして、「発明は必要の母」という逆転の発想。
この講演を通じ、私にとっても、“未来を想像する力”の大切さを改めて感じた一日でした。
なお、本記事は筆者個人の理解・所感によるものであり、
講演者の公式な見解や所属団体の立場を示すものではありません。